2025.10.24

2025年8月22日に横浜国立大学 先端科学高等研究院(IAS)の先進化学エネルギ研究センター(ACERC)によるシンポジウムを横浜国大キャンパスにて開催されました。
冒頭の梅原 出 横浜国立大学長・高等研究院長による開会挨拶、東京科学大学附属高等学校 梶原将校長に来賓のご挨拶をいただいたあと、ACERCのセンター長 光島重徳教授の「エネルギーの歴史とカーボンニュートラル、水素と水の反応の物理と化学から水素エネルギー社会」、同センター先進蓄電地研究ラボ長/英国王立科学会フェロー 藪内直明教授の「蓄電池とエネルギー貯蔵技術の進展が拓く未来-脱化石燃料依存へ向けて」が10代を中心とした若い世代の参加者に専門内容を判りやすくかつ歴史的・俯瞰的な視点を自らの想いも込めて語られました。
さらに、横浜国立大学 環境情報学府人工環境専攻 博士課程2年の纐纈さんからは「クレーン訓練で切り拓け!”月面水素社会”」として、若手研究者が拓く未来について熱く語られました。
高校、高専からも行われ、東京科学大学附属科学技術高等学校からは「アセチル化を経由したワンポットセルロース糖化方法の開発」、神奈川県立横須賀高等学校からは「二酸化炭素をエネルギー資源にしよう」、東京工業高等専門学校からは「マイクロウェーブ法と誘導加熱法を組み合わせたFe/N/C型非白金系酸素還元触媒の迅速省エネルギー調製法」がありました。いずれも実験結果報告に留まることなく、これからの課題・目標についても高い視点の発表であり、会場の参加者との多面的な意見交換に繋がりました。
続いて行われた、「YNUダイアログ(対話セッション)」では、光島教授、藪内教授、纐纈さんをパネリストに迎え、会場の参加者も交えての「2050年カーボンニュートラル社会のためのサーキュラーエコノミーを考えよう」というテーマのもと、若い世代の視点・意見を元に対話を行いました。
最後は研究室見学を行い、参加者には参加証、発表者には奨励賞が授与され、全てのプログラムを終了しました。
※ 本記事内の所属及び役職は全てシンポジウム開催時点のものです
目次
開会挨拶
開会挨拶に登壇した 梅原 出 横浜国立大学長・高等研究院長 は、「大学の高等研究院ような研究に特化した組織でも一般向けのアウトリーチする柔軟性が求められるようになっている。普段大学研究者は若い人との対話機会が少ない。この機会を楽しみにしているとともに、大学側からは皆さんにわかりやすい説明を、皆さんからは日頃の活動の成果が良い形で表れることを期待している。」とシンポジウム開催への期待を込めて開会を宣言しました。
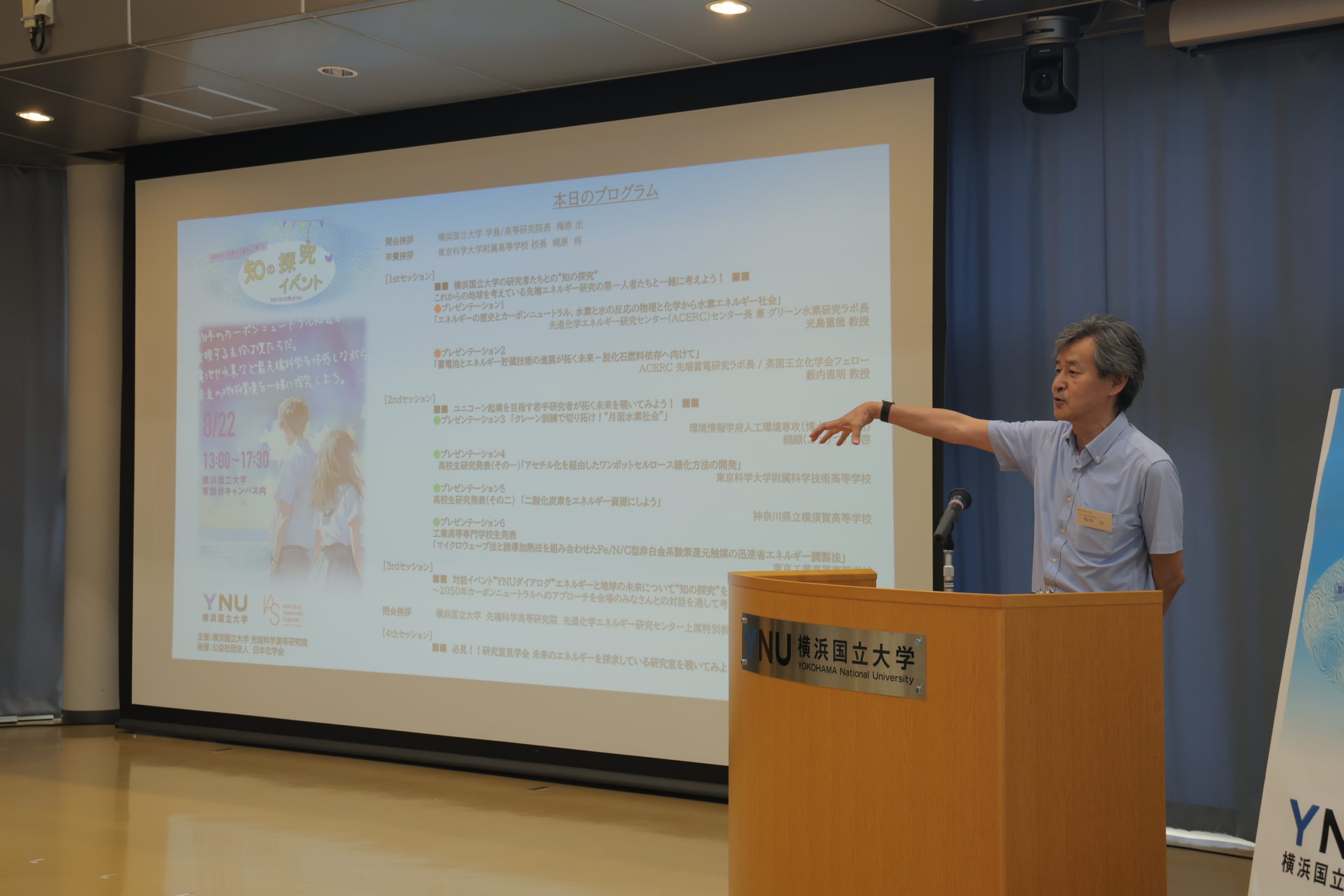
来賓挨拶
来賓としてご挨拶いただいた東京科学大学附属科学技術高等学校の梶原 将校長は、パリ協定におけるカーボンニュートラル目標(2050年のカーボンニュートラル達成、2030年までにCO2を45%削減)に触れ、今日の技術研究の専門家と若い世代の人々が知識共有し、議論したことを更に伝え広げていくことで、世界の大きなうねりにつながってほしいとの想いを語られました。

[1stセッション] 横浜国立大学の研究者たちとの“知の探究“
これからの地球を考えている先端エネルギー研究の第一人者たちと一緒に考えよう!
Ist セッションでは、横浜国立大学の先端化学エネルギー研究センターからカーボンニュートラル(CN)の実現に向けたエネルギーと蓄電池技術について講演が行われました。
●プレゼンテーション1
「エネルギーの歴史とカーボンニュートラル、水素と水の反応の物理と化学から水素エネルギー社会」
先進化学エネルギー研究センター(ACERC)センター長 兼 グリーン水素研究ラボ長の光島重徳教授は「エネルギーと人類の歴史」、「カーボンニュートラルと水素エネルギー社会」という二つの切り口でカーボンニュートラル社会のあり方を講演しました。
1. エネルギーと人類の歴史
エネルギーというキーワードで人類の歴史を振り返り、数億年かけて堆積した化石エネルギーは、人類が火を発見してからの歴史(約700万年)から見ると、ごく短期間で大量に使用されているという現状を指摘しました 。
人類の発展は「怠ける」方向への発展であり、火の発見(内臓の小型化、脳の発達)、農業革命(筋肉の代替)、記憶の代替(紙、印刷)、産業革命(熱エネルギーを動力へ)、電動化・電気(動力の伝達、通信)、そして現代のAI(考えることの代替)へと進んでいると分析 し、人類の認知革命・農業革命・科学革命・産業革命・電動化・AIの進展が、エネルギーの形態変換(化学→熱→動力→電力→情報)と人類の身体・記憶・労働の外部化を促進し、人類史のスパン(7万年〜100万年)からみて産業革命以降たった数百年でこれだけのエネルギーを使ってる今の常識は長い歴史から見たら非常識といえる状況であると語りました。
2. カーボンニュートラルと水素エネルギー社会
有望なエネルギー源として風力と太陽光を挙げるもこれらは不安定なエネルギー源であり、これらを用いて水を電気分解して水素をつくり、化学エネルギーとして電力系統の安定化(蓄電池)や長距離・長時間のエネルギー貯蔵・輸送を行う水素エネルギー社会が重要になると強調するとともに、エネルギーは運動、位置、電気、熱など多様な形態を持つが、その本質は「粒子の運動と相互作用」に還元できるものであり、電気化学は、物質と電気エネルギーを相互変換するという点で、カーボンニュートラルを考える上で非常に重要な技術分野であることを判りやすく説明しました。最後に日本がカーボンニュートラルを実現するためには、輸入化石燃料に頼る現在のエネルギー自給率を改善し、再エネと水素エネルギーで賄う社会のあり方を語りました。

●プレゼンテーション2
「蓄電池とエネルギー貯蔵技術の進展が拓く未来-脱化石燃料依存へ向けて」
ACERC 先端蓄電研究ラボ長 / 英国王立化学会フェロー 藪内直明 教授は蓄電池技術を通してのカーボンニュートラル社会について講演を行いました。
1. 再生可能エネルギーと蓄電池の重要性
カーボンニュートラル達成の鍵は、不安定な太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギー(再エネ)をいかに使いこなすかにあると指摘しました。 再エネは導入コストが劇的に下がり、既に火力や原子力を下回る可能性も出てくる中で、この不安定な再エネの電力を安定化させ系統電力に大量に導入するために不可欠なカギが蓄電池と語りました。
2. 電気自動車(EV)の現状と課題
EVの懸念点であった航続距離と電池寿命は技術改良により克服されつつあり、世界の新車販売台数に占める割合は日本ではまだ3%ですが中国や欧州を中心に20%近くに達しています。 現在残されている最大の課題が充電時間の長さであり、これを解決するために自宅の電力系統に組み込むV2H(Vehicle to Home)や、1.2GW級の超高出力充電器の開発が進んでいることを紹介しました。
3. Liイオン電池の進化と次世代技術
Liイオン電池は過去30年間で価格が97%低下という驚異的な進歩を遂げ、EVや定置用蓄電池の普及を支えてきました。しかし、Liイオン電池の有機溶媒に起因する火災リスクをゼロにする不燃性の固体電解質を用いた全固体電池、安価で資源豊富な元素へ移行すべく高性能なコバルトフリーニッケル系材料やマンガン系正極材料の開発が進められています。さらにはプロトン蓄電池(水素・水を利用)を利用した安価で安全な電池を目指した開発などを推し進めることが極めて重要であると締めくくりました。

[2ndセッション]
ユニコーン起業を目指す若手研究者が拓く未来を覗いてみよう!
2ndセッションでは大学院在学でユニコーン起業を目指す若手研究者の発表をはじめとして高専・高校での将来を担う研究者の卵たちの取組について発表がありました。
●プレゼンテーション3
「クレーン訓練で切り拓け!”月面水素社会”」
横浜国立大学 環境情報学府人工環境専攻(博士課程後期)の纐纈(こうけつ) 真啓さんは、グリーン水素社会の地球側の実装事例、アルテミス計画による月面資源利用と持続可能拠点構築、そして月面作業にも応用可能なVRクレーン運転訓練と遠隔操作の予測制御技術という、三つの最先端テーマを横断的に融合させた未来を創る月面水素社会の魅力を語りました。特に、月の南極・北極の永久影には氷が何十億年も保存されていると考えられており、この氷を採掘し、電気分解することで、人間の活動に必要な水・酸素や、火星に向けたロケットの推進燃料(水素・酸素)を重力が地球の1/6の月で製造することには戦略的な利点があることを強調しました。また、これら先端技術の研究成果を社会に届けるために、スタートアップの立ち上げが有効な選択肢であるとの提案がありました。最後に参加者に対し、「皆さん、どんな関わり方を選びますか」と問いかけ、専門分野の深堀りだけでなく多様な分野を横断的に融合し新しい価値を創出する「異分野融合」の重要性を強調しました。

●プレゼンテーション4
「アセチル化を経由したワンポットセルロース糖化方法の開発」
東京科学大学附属科学技術高等学校の川島美遥さん、鈴木結葵さん、松久保瑛太さんによる発表は化石燃料の枯渇や地球温暖化対策として食料と競合しない木材などのセルロース系バイオマスからバイオ燃料を生成する技術に注目した研究でした。セルロースは水素結合により強固に結合しており分解が困難という課題に対し、セルロースをアセチル化することで溶解性を高め、固体酸触媒を用いた糖化反応を効率化し、さらにこれらを同一容器内で行う「ワンポット合成」というユニークなアイディアで高効率な糖化方法を模索するものでした。今後は、アセチル化に用いる無水酢酸の量を最適化し、最小限のコストで最大限の効果を目指すとともに、廃材や間伐材などの実際のセルロース系バイオマスを活用した実証実験を行っていく目標を語っていただきました。

●プレゼンテーション5
高校生研究発表(その二) 「二酸化炭素をエネルギー資源にしよう」
神奈川県立横須賀高等学校の木下功貴さん、若宮亜門さん、五十嵐涼子さんによる発表は、石油や石炭の燃焼による二酸化炭素濃度の上昇とそれに伴う地球温暖化問題に対し、身近な金属を電極に用いて二酸化炭素をエネルギー資源化するという着眼点に立って、二酸化炭素をメタンやエチレンなどに還元しエネルギーとして再利用する方法を研究したものでした。触媒となる金属電極、特にメタンやエチレンを生成する「銅」に注目し、身近な銅合金である硬貨を用いてその効率を比較検証したところ、純粋な銅板よりも合金である10円玉の方が高い効率を示すことが判りました。また、銅以外の含有金属(亜鉛など)も反応に影響を示唆されていること、エネルギー変換効率の計算から、水素が約12-13%、メタンが約34%、エチレンが約53%となり、エチレンへの変換が最も効率的なことを確認できたことの発表がありました。

●プレゼンテーション6
「マイクロウェーブ法と誘導加熱法を組み合わせたFe/N/C型非白金系酸素還元触媒の迅速省エネルギー調製法」
東京工業高等専門学校の小原智也さんによる発表は、家庭用燃料電池やモビリティへの応用可能性のある燃料電池向けFe–N–C系酸素還元触媒の省エネルギー合成法に関する研究成果の紹介でした。従来の高温焼成に対し、誘導加熱とマイクロ波を組み合わせることで、大幅な所要時間短縮、消費電力削減を達成できる可能性を乾燥法、粉砕有無、加熱時間などの比較データを踏まえて紹介されました。

[3rdセッション] “YNUダイアログ”
エネルギーと地球の未来について“知の探究”を掘り下げよう
■ダイアログパートナー
光島重徳 教授:ACERCセンター長 兼 グリーン水素研究ラボ長
藪内直明 教授:ACERC 先端蓄電研究ラボ長 / 英国王立化学会フェロー
纐纈真啓 さん:環境情報学府人工環境専攻(博士課程後期)
■ファシリテーター
内田雄基 さん:ニッポン放送アナウンサー
このセッションではシンポジウムの司会を務めていただいたニッポン放送の内田雄基アナウンサーがファシリテーターを担当し、多様な人たちが対話を通し学び合うユニークな取組み、「YNU Dialogue」として、会場の方も参加する形で開催しました。ダイアログパートナーの3名の方と『2050年カーボンニュートラル社会のためのサーキュラーエコノミーを考えよう』を共通の「問い」として対話が行われました。会場からの積極的な質問や意見が寄せられ、登壇者と共に自分たちの課題として「問い」と向き合う有益な時間となりました。




閉会挨拶
閉会の挨拶では横浜国立大学 先端科学高等研究院 先進化学エネルギー研究センター上席特別教授 渡邉正義氏が登壇しました。渡邉教授は参加者に対して自身の専門性を深く追求すると同時に、一つの解決策で全てが解決するわけではないことを念頭に、幅広い視点を持って今後の勉学に取り組むよう激励しました。また、技術があっても外交関係や安全保障が確保されなければ社会実装は困難であると事例を示しながら科学技術の発展を支える「複眼的な視野」の重要性を強調し、会を締め括る言葉としました。

[4thセッション]
必見!!研究室見学会 未来のエネルギーを探求している研究室を覗いてみよう!
シンポジウム終了後は参加証を、発表者には奨励賞を渡すと共に、オープンキャンパスでは体験できない実際の研究室の中に入って、具体的な研究活動を覗くツアーを開催し、好評を得ました。





